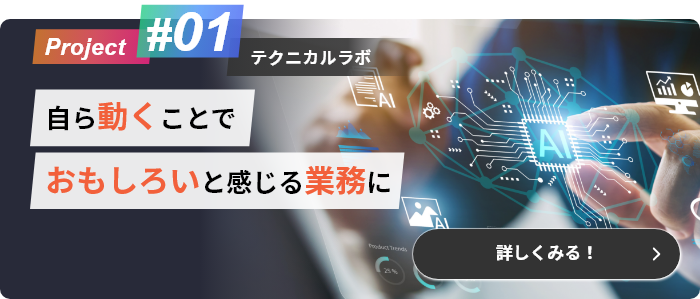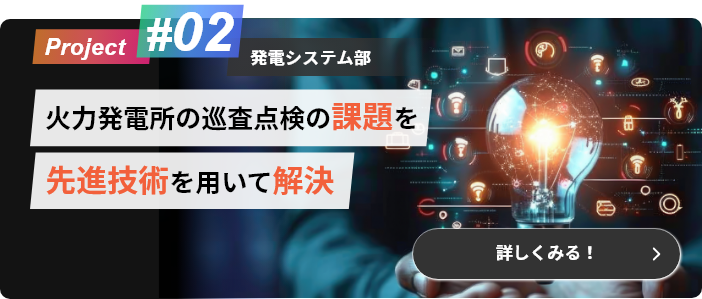関西電力送配電における現場出動業務(電気の利用者の元へ出向き、引っ越し時の手続きや停電等の申出の対処を行う業務)において、これまで利用していたハンディターミナルのリプレースをすることとなった。
主に停電の復旧等で現場の業務をより円滑に行うため、最新の情報をよりリアルに把握できるように、ハンディターミナルをiPhoneにリプレースしたいという要望から、当プロジェクトが開始された。
iPhoneの導入に伴い、サーバサイドのアプリケーションの開発が必要となったが、要望事項の整理・検討の結果、SaaSを導入することとなった。
当プロジェクトは災害時の停電復旧をより円滑に行えるようにするというミッションがありながら、大規模SaaSの導入、iPhoneアプリの開発という、非常に挑戦的なプロジェクトとなった。
Project
#03
新たな挑戦の先に
価値のあるシステム
Project Member
託送システム部
託送OSSシステム第1グループ
-

2013年度 入社
-

2010年度 入社
-

2011年度 入社
挑戦的なプロジェクトの
スタート
次々と発生する課題
案件の経緯でも述べた通り、当プロジェクトは、大規模SaaSの導入、iPhoneアプリの開発という関西電力送配電としても関電システムズとしても、新しい挑戦だった。
社内での前例もほぼなく、次々出てくる課題に対して、手探りで進めていく場面も多かった。

SaaSの導入に当たっては、まず、様々な制約が課された。
スクラッチ開発と違い、SaaSの既存仕様では利用企業内の標準として定められているセキュリティルールの要件に100%合致しないこともある。その中で、関係者と調整しながら、セキュリティ要件を下げることなく柔軟に対応し、適合してていくことには苦心した。セキュリティ要件と同様、業務の面でもSaaSの制約の影響はある。画面表示、操作などについてのユーザからの要望に対し、SaaSでは実現できないものもあった。
さらに、従来は電気を利用するお客さまからの申出の受付から現場出動まで一貫して1つのシステムで行っていた業務を、受付業務はそのままに、現場出動業務のみをSaaSに移管することになっていたため、既存システムとSaaSの双方で更新されるデータを互いに連携し合うという新旧融合も、難易度を高めた要因の一つである。SaaSの制約だけでなく、システム間で連携するデータの整合性の確保のためにユーザのご希望に添えないという場面もしばしばあった。その都度、代替案の提案、説明および調整を重ね、ユーザにご理解いただくと共に、お互いに納得のいく結論に落とし込んでいくということは一筋縄ではいかないものであった。
また、iPhoneアプリの開発も、開発方針の確定まで紆余曲折を経ることとなった。
プロジェクト発足当初はWindowsタブレットでの開発が予定されていたが、ユーザの環境変化に伴い、iPhoneアプリでの開発へ変更となった。当時は、当社でiPhoneアプリの開発事例がほぼ無く、開発環境も整っていない状態だったが、開発の目途を立て、一度は既存アプリケーションの機能を移植すれば良いというところまできたが、そのタイミングでSaaSアプリだけで作業を完結するようニーズが挙がったのである。
その結果、計器を操作する処理だけはSaaSアプリで実現できないため、既存機能をSaaSアプリとスクラッチ開発の2つのアプリに分ける必要性に迫られることとなった。
プロジェクトを通して、どの開発領域も試行錯誤の繰り返しであった。
新しい視点を取り入れることで
よりよいシステムを構築できる
苦労したことが、成長へと繋がったと実感できる。システム要件として、関西電力、関西電力送配電はITに関する様々な規定・ルールが細かく定められているため、重要システムでのSaaS利用は難しいという先入観があり、実際に様々な制約に頭を悩ませた。

しかし、今回のプロジェクトで、関係各所との代替方式の検討・調整やクラウド(AWS)等の活用を経験したことで、その先入観を打ち破ることができた。単独のサービスや機能、技術では要件を満たせないことも、他の要素とうまく組み合わせることで実現不可能な要件はないのではないかと考えるようになった。業務要件としては、システムの刷新のため、現行システムの機能を調査すると共に、その機能が業務の中のどのような場面に使用されているのか、何に不便を感じていて、それを刷新後にSaaSを使ってどのようにしてきたいのか、という話を伺う機会が多くあった。
また、開発者の立場からは、従来のハンディターミナルで1つのアプリケーションで提供していた機能を、2つのアプリに分けることには抵抗があり、何度も議論を重ねて開発を行っていても、品質や操作性に対する懸念が拭えなかったが、リリース後の問合せ内容を確認すると、最初は戸惑う部分もあったものの、新しいシステムでの運用を前向きに進めていただけていた。UIの変更など品質、操作性に影響する変更はユーザからのクレームに繋がるため、極力避けるべきだと考えていたが、ユーザ含めた関係者の考えを統一させることができれば、大幅な変更もできるのだと学んだ。1つの機能を挙げても、誰が、いつ、何のために使うかによって、その機能を追加すべき画面が変わったり、統合・分割か可能となったり、そもそも自動化することができる可能性さえ出てくる。固定概念にとらわれず、お客さまの「業務」の視点でユーザにとって利便性の高いシステムを構築するというを強く意識するようになった。


今後の目標
当社は「ITでお客さまの業務を低コストでカイゼンしていくこと」が求められている。
以前はお客さまから提示された要件に対して開発を行うことが主であったが、近年、要件定義などの上流工程に力を入れている。今後も様々なプロジェクトで上流工程から参画して経験を重ね、システム開発・維持運用とお客さま業務、双方にとってより良いシステムの提案、構築に貢献できるよう努めていきたい。
以前はスクラッチ開発が主流であり、外部製品の利用は選択肢として挙がっていなかったが、昨今はまず製品利用の検討を求められている。製品には制約が多く、選定を誤ってしまえばスクラッチ開発でカバーすることも難しくコストに見合ったシステムが構築できないため、構築するシステムにあった構成を提案できるように視野を広げてシステム開発に取り組んでいきたい。
新しい技術に触れるのは最初はストレスに感じることがあるが、やっていくうちに面白くなるもので、それはプロジェクトにも同じことが言える。これからも新しい技術を取り入れながら、価値あるシステムを作れる人財になれるように日々精進したい。