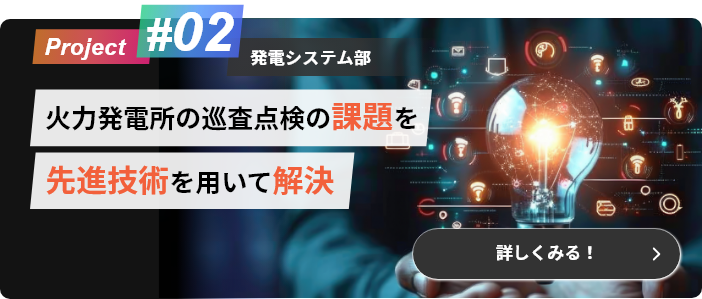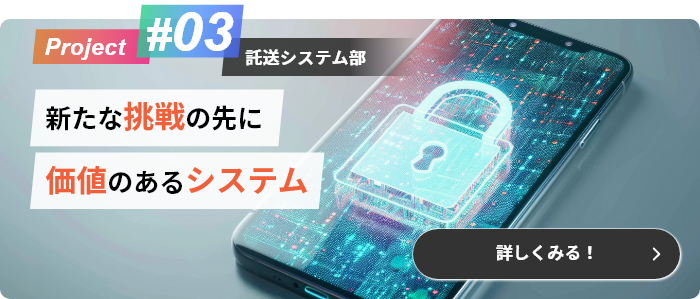生成AI開発プロジェクトはプロジェクトメンバーが自ら提案したもので、生成AIをシステム開発や運用に適用することを前提として成果物作成の流れを再定義し、各工程に係る時間を圧倒的に短縮させ、効率化を図ることを目的としたプロジェクトである。
生成AIの有効性に注目され始めたころからこの技術に着目しており、2023年のAI推進グループ発足をきっかけに提案し、現在まで生成AIのシステム開発への標準化を目指している。
関電システムズは、関西電力・関西電力送配電の事業を支えるITシステムの開発から運用・保守までを手がける会社であり、当社は電力の需給バランスから電力所や変電所などに配備されている設備の管理、電力供給世帯に配備されているスマートメーターの管理や施設の入退室、勤怠など、ありとあらゆるシステムを開発・運用している。AI産業革命に備えるため、関電システムズではこれらのベース技術であるAIの導入・推進に日々取り組んでいる。
着手当初は担当者2名だけで適用可能性を探る程度の規模で技術検証を行っていたが、実際の開発案件に適用する並行開発に生成AIを適用した結果、プロトタイプ(試作品)制作にかかる時間を圧倒的に短縮できる効果を2023年に報告したことをきっかけにAI-Nativeプロジェクトが本格的に稼働した。
Project
#01
自ら動くことで
おもしろいと感じる業務に
Project Member
テクニカルラボ DevOps推進グループ
-

2014年度 入社
-

2018年度 入社
自ら提案を行った
新たなプロジェクトの始動
膨大な検証と人員不足

本取組みはシーズ技術があって、それを業務フィッティングできると考えたものであり、必ず効率化できるという根拠があったわけではなかったことから、まずこれを検証し、効果があるという結果を示していかないといけないところからスタート。
そのため、検証の対象を決定するために現行業務の棚卸から始めたが、開発や運用・保守の工程を作業レベルまで細分化していくと、かなり検証すべき項目が出てきたため、限られた人数でこれにすべて同時並行で対応していくのは不可能。そのため、優先度をつけて対応するも、対応する手が足りない状況が続いた。
また、これらの検証結果をとりまとめ、成果として報告することも必要だが、同時に展開を見据えたときに、マニュアル化や標準化の取組みも行わないとならず、技術検証作業以外にも作業の手が取られてしまい、とても苦労した。
プロジェクトを通して気付けた会社のサポート

途上の取組みであり、今後まだまだ対応継続中であるが、システムインテグレーションの様々な工程に適用できる手ごたえは感じている。
この取組みを始めた大きな気づきとしては、自分たちの想像以上に、会社が自分たちがやろうとしていることをバックアップしてくれているということ。もちろん、上司等へのコンセンサスは重要であることは理解していたが、問題視や指摘などは全くなく、むしろ企業の取組計画の中に積極的に組み入れるといった配慮までいただき、会社からも全面的に支援をいただいて取組みを進めることになったため、モチベーションは非常に高い状態を保てている。
これからも、自分が実現したい・挑戦したいと思うことを、会社の実現したいことにマッチさせ、会社の未来を自ら切り拓いていきたい。
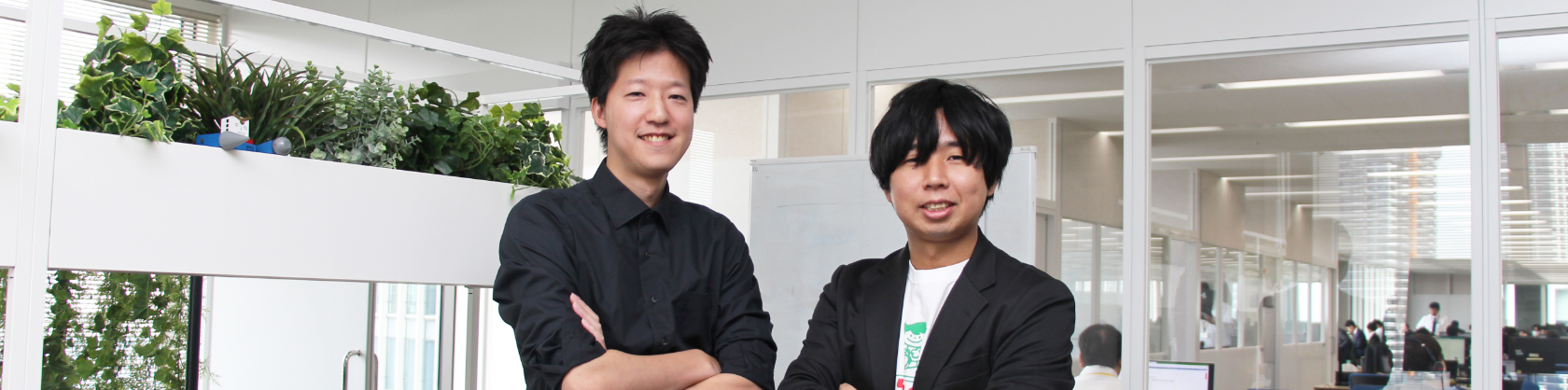
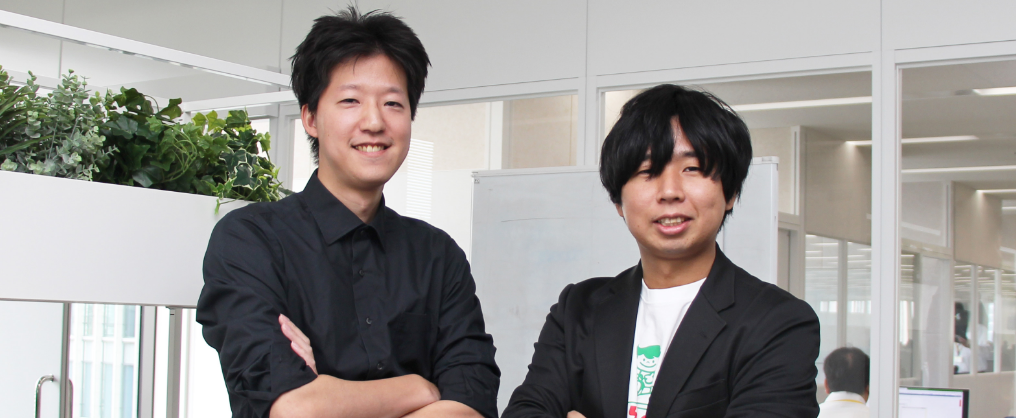
新しい技術に挑戦し続け自らの目標を達成する
AI-Nativeプロジェクトの完遂がこの取組みのゴール。
これまでやってきた開発や運用スタイルを抜本的に見直し変えていくことになるため、開発・保守・運用現場の戸惑いや反発は想像に易く、システム開発の各プロセスへの適用可能性を一つ一つ丁寧に検証し、マニュアル・標準化を行っている。そのため検証にはかなり時間を要しており、現在は本プロジェクトへのリソースを追加投入することで、プロジェクト進捗スピードを向上させているところである。実際の業務への適用による効果は計り知れず、いち早く展開することで開発・保守・運用を効率化していきたいと考えている。
また、この取組みの最中にもAI技術の進化は止まらず、次々と新たな技術やサービスが展開されていっており、プロジェクト推進と並行してこれらをキャッチアップし、プロジェクトに取り込んでいくことも行っている。最たる例がCode Copilotであり、現在はこの技術やサービスなどの導入に向けた技術検証も並行して行っている。
このように、プロジェクトを進めていく中で出てくる問題や課題だけに対応するのではなく、世の中の技術革新や進展スピードを適切に捉え、業務にマッチしそうなものを的確にキャッチアップすることも同時に行い検討していく。先進技術をSIに組み込むのは大変だが、社会で注目を集めているトレンド技術を業務適用することは知的好奇心をくすぐるもので、刺激的でおもしろい。自らが目指したい業務・開発のあり方をこれからもどんどん提案し、挑戦を楽しんでいきたいと考えている。